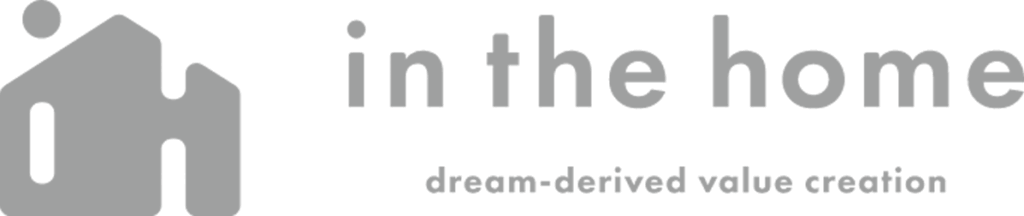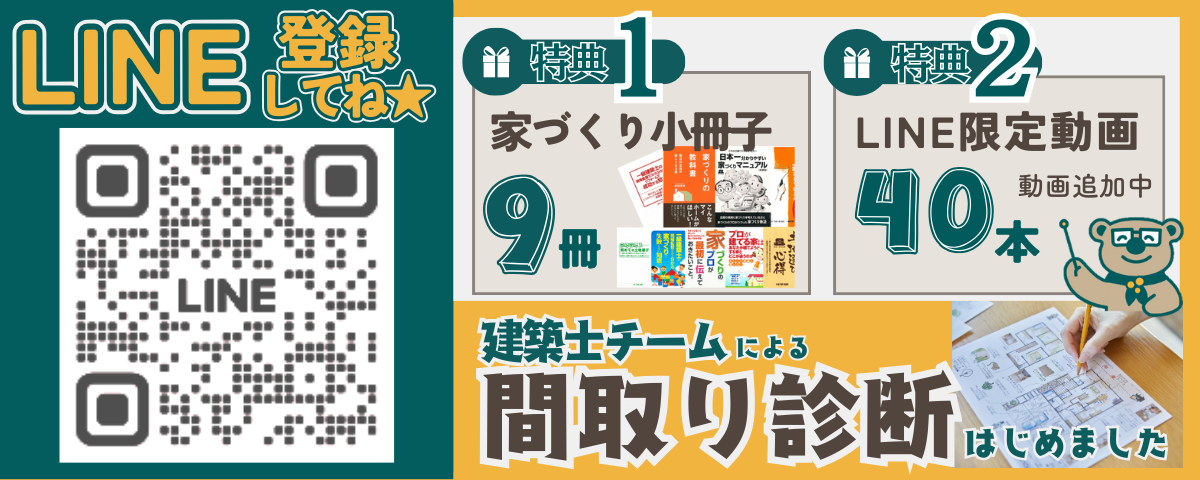こんにちは、前田です。
地盤判定についての相談がありました。
残念ながら・・・
未だに地盤調査をいい加減にしている住宅会社や建築がいます。
相談の内容は・・・・
- 契約に地盤補強は含まれている(70万円)
- 地質調査報告書はもらっていない
- 地盤は問題ないので補強はしなくても良いと建築士に言われた
- 確認の為に調査報告書をもらったが、そこには地盤改良が必要と記載があった
- 建築士の判断で必要ないと言われた
こうやって書かれると何か変だと感じるかも知れませんが
相談者にとっては、なかなか行動に移せないし
「建築士だから大丈夫でしょ。会社も大きいしもんだいないよね。」
と自分を納得させる事で安心をしていたようです。
そこで、地質調査報告書をみせてもらったら
自沈層が2m付近にあり、私が設計するのなら必ず補強する地盤だったのです。

これ、本当の話です。
建築士だからって安心出来ません。
そこで、地盤判定をするのにみるべき事を簡単にお伝えします。
地質によって検討事項がちがうので注意が必要です。
①基礎底盤より自沈の確認
2mの深さまで1000Nで自沈
2~5まで 500Nで自沈
これが地盤改良判定の基準になります。
もっと分かりやすく言うと
100㎏のおもりでロッドがズブズブと沈む自沈する層が2mまでにある
50㎏のおもりでロッドがズブズブと沈む自沈する層が2~5m(3m間)までにある
この場合は、沈下の検討をします。
②粘性土と砂質土の場合
粘性土の場合は圧密沈下の検討をします。
圧密沈下とは、粘性土の水分が建物の重量で抜けてしまい、沈下する現象です。
10年以上の長い期間でゆっくり沈下していきます。

沈下量・傾き・傾斜角など検討していきます。
砂質土の場合は、液状化の検討をします。
液状化マップがありますので、土地選びの際には参考にしてください。

こうなってしまうとライフラインもダメなので
あまりお勧め出来る土地ではありません。
③地盤の許容応力度算出
基礎形状を決めて、接地圧の検討をします。
地盤によっては、ベタ基礎だから安心とはなりません。